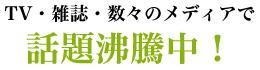FROM 安永周平
昨日から、何やら鼻がムズムズ…
鼻水がズルズルしたかと思えば、
なんだか頭がボーッとする。。。
なんと、33年間生きてきて、
ついにデビューしてしまうのか。
その一方で「認めたくない」
という思いと戦いながら、
「あぁ、最近ストレスが
溜まってんのかなぁ〜。」
と自分に言い訳しながら、
最近の自分を振り返ってました。
とはいえ、今この瞬間にも
鼻水は出てくるわけでして…笑
なんかすぐに効くものないかと
思っていたところ、ちょっと
興味深い内容を見つけました。
それは「ワセリン」を鼻の中に
塗ると花粉症が予防できる…と。
ワセリンとは、皮膚を保護する
天然由来の保湿剤のことです。
肌の内部には浸透せずに
塗った肌の表面にとどまって、
ホコリや物質から守る働きを
してくれるもので、この場合は
花粉が鼻の中には付着せずに
ワセリンが防いでくれる…と。
どうやらTwitter等では
かなり話題になっているようで、
感想をみんな投稿している模様…
『すげええええワセリン塗ったら
マジでくしゃみ止まった 神かよ!』
『まさにそれやってます!
人の3倍アレルギーがある自分でも、
今のところ、快適です。』
『花粉症を三十年くらいやってますが、
去年知った”ワセリンを塗る”は、
一番効果があるかも知れない。』
そんな書き込みがあったので、
僕も今日は家にあったワセリンで
試そうかと思ったのですが…
ひと晩グッスリ眠ったら、
なんか鼻水止まってましたので
塗るのすっかり忘れてました笑
ですので、その効果のほどは
分からないのですが…今すぐに
何とかしたい…という方には
オススメかもしれませんよ。
(※あくまで自己責任ですが…)
というのも、理屈で考えれば、
ワセリンで鼻の中の粘膜に花粉が
付着することができるのなら、
それは効果的だと思うのです。
それは、花粉症の起こる
メカニズムを知ると分かります。
まず、空気中のスギ花粉が、
人間の鼻の中の粘膜に付着すると、
その花粉は粘液として溶け出します。
その粘液となった花粉がリンパ球の1つ
であるマクロファージに取り込まれて、
その情報は「Tヘルパー細胞」と
呼ばれる細胞に伝達されます。
その際、Tヘルパー細胞が、
侵入してきた花粉を誤って
「敵」とみなしてしまうと、今度は
その情報がB細胞という細胞に伝達され、
B細胞は敵とみなされた花粉に対抗する
IgE抗体を、その都度つくり出します。
このIgE抗体は、結合しやすい
顆粒球の肥満細胞と結合するため、
花粉と接触するたびに作り出される
IgE抗体は、カラダの中に
大量に蓄積されていきます。
こうしてIgE抗体が蓄積され、
あるレベルに達すると、
花粉症などのアレルギー反応の
準備が出来上がった状態になります。
この状態で、再び花粉に
接触すると、クシャミ・鼻水などの
花粉症の初期症状が現れるのです。
そしてさらに花粉が侵入すると、
IgE抗体が花粉をキャッチして
結合する…この繰り返しが
刺激となって肥満細胞が活性化し、
体内でヒスタミンなどの
化学伝達物質が放出されます。
これらが過剰に毛細血管や
知覚神経を刺激するために、
花粉が侵入する鼻や目の回りに
炎症が起こってしまい、クシャミや
鼻水、目のかゆみなどをともなう、
つらい花粉症となるというです…
まぁ小難しいことを書きましたが…
要は、症状が起こるキッカケは
やはり花粉であるわけですから、
それをシャットアウトするのは
「対処療法」としては合理的。
ですから、傷口に絆創膏を貼るのと
同じように、今すぐに何とかしたい
人にはいいのかもしれませんね♪
* * *
ちなみに、おのころ心平の元には
過去に花粉症でカウンセリングに
訪れた方もたくさんいたのですが…
そういった方々は、
どちらかというと対策グッズより
自分の「自然治癒力」をもって、
花粉症を克服していったケースが
多かったようなのです。
それに、先に書いた
花粉症のメカニズムにしても…
必ずしも花粉が原因ではなく、
やはりカラダの免疫のバランスが
崩れてしまったことによって
発症しているとも言えるわけで。
このあたり、カラダや免疫の
機能について学ぶことによって
対策グッズに頼らずとも花粉症を
克服できる可能性はあります。
今すぐ…というわけにはいきませんが
もし、あなたが興味があるのなら、
こちらのページをチェックしてみては?
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「もしかしたら花粉症かも・・・」
という安永の言葉を聞いて、
「そうなんだ!実は、花粉症になる
タイプの一面も持っていたんだ!」
と、心の中でこっそり
喜んでいたのですが違うようですね…
人それぞれに持ち味があるので
安永が花粉症じゃなくて
ある意味良かったです(笑)
ー剱悠子
PS
花粉症になりやすいタイプ
というのがあるんですが、
編集後記で書くには長くなるので
気になる方はこの講座で
おのころ先生から直接
教えてもらってください
>>メルマガの購読はコチラから