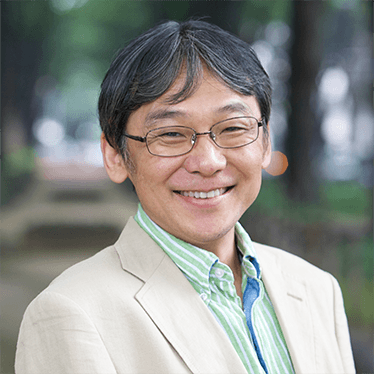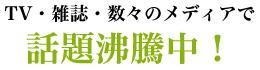FROM 川嶋朗
気にはいいものと悪いものがあり、
悪い気は邪気と呼ばれます。
たとえば邪気の1つに
風邪(ふうじゃ)と呼ばれるものがあります。
風邪(ふうじゃ)が風という字のつく
つぼから体内に入ってくると、
その名のとおり、風邪(かぜ)をひいてしまいます。
風邪をひきそうになると、
背筋がゾクゾクっとすることがあるでしょう。
それは風という字のつく
つぼが首の後ろにあり、
そこから風邪(ふうじゃ)が
入ろうとしているから。
昔の人はうまく考えたものです。
ところで、
風(邪)というのは
東洋医学における外因の1つです。
東洋医学には
「病気の原因は内因と外因、
そして不内外因の3つにある」
という考え方があり、
心的な病気を内因、
自然環境や気候などによる
環境的な原因を外因、
それ以外のすべての原因を不内外因と呼びます。
そして内因、外因、不内外因が
人間の心や体に影響を与えると、
自律神経や免疫のバランスが崩れ、
自己治癒力が低下します。
要するに、ホメオダイナミクスが
維持できなくなるわけです。
内因は七情とも呼ばれ、
喜・怒・憂・思・悲・恐・驚
という感情が含まれます。
一方、
外因は六淫(りくいん)ともいい、
風以外に、寒・暑(熱)・湿・燥・火
という環境要因を含みます。
そして不内外因には
遺伝子異常や食生活、生活習慣など、
内因・外因以外のすべての要因が含まれるのです。
風邪(ふうじゃ)のように
邪気として直接作用しなくても、
内因・外因・不内外因が
気の正常な流れを妨げたり、
気のバランスを崩したりすることもあります。
たとえば、
何となく喉の辺りに何か詰まったような、
もやもやした感じがすることがあるでしょう。
これは
悲しみや怒りの感情がストレスになり、
喉に気がたまって流れなくなった状態です。
西洋医学ではヒステリー球、
漢方医学では梅核気(ばいかくき)
あるいは咽中炙臠(いんちゅうしゃれん)
と呼ばれる病態で、鍼や気功など、
気を正しく流してあげる処方をすれば回復します。
気はバランスがとれていることも非常に大切です。
気が少なければエネルギー不足に
なるのはもちろんですが、
多すぎるのもよくありません。
余分な気が邪気となり、体の中に
たまってしまう可能性があるからです。
体内に邪気がたまった状態が邪実であり、
体内に出さないまま放っておけば
病気の原因となります。
ただし、同じ要因を受けた人に
同じ症状が現れるわけではありません。
どんな症状が体に現れるかは、
その人の体質によって変わってきます。
同じ人であっても、年齢や
生活環境によって症状は変わるでしょう。
ですから、漢方医学では
患者さんの病状だけでなく、
体質や基礎体力などを総合的に診断し、
その人の体質に合った治療を提供します。
要するに、違う病気でも
同じ処方をすることもあるし、
同じ病気でも違う処方をすることがあるのです。
漢方医学では、これを
異病同治・同病異治といいます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━
先週末から、久しぶりに
風邪を引いていました(笑)
内因、外因、不内外因、、、
思い当たることが多すぎて何かは
分からないけど、気が多すぎて
バランス崩しちゃった感は否めません…
けれど、これを読みながら、
最近の自分の行動や感情を
振り返ることができたのは
良い機会だったなぁと喜んでます♪
ー 剱 悠子
PS
こちらのバランスも理想に近づけたいです
↓
こちらへ