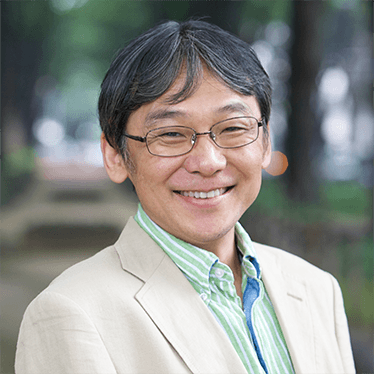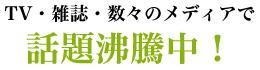FROM 川嶋朗
抗がん剤は「やめどき」が難しい、といいます。
特に、少しでも効いている場合、
患者さんはその抗がん剤をやめることができません。
また、効果が上がっているうちは、
たとえ患者さんが副作用に苦しんでいたとしても、
医者は「そろそろ抗がん剤をやめたほうがいい」とは
なかなか言えません。
仮に抗がん剤の投与をやめ、
患者さんの容態が悪化したり、亡くなったりしたら、
あとで患者さんやその家族から責任を問われたり、
医療訴訟を起こされたりするおそれがあるからです。
しかし、同じ抗がん剤を使い続けていると、
やがてがん細胞はその抗がん剤に対し、
耐性を持つようになることがあります。
最初のうちはめざましい効果があっても、
いつかは効かなくなるときがくるかもしれません。
すると、今まで攻撃される一方だった
がん細胞たちが、反撃を始め、
逆に症状が悪化するようになります。
これが「リバウンド」です。
使っていた抗がん剤が効かなくなると、
医者は別の抗がん剤に切り替えますが、
やがてそれも効かなくなる可能性があります。
がんの治療においては、
がんが進行する前にできるだけ叩いておくため、
最初のころは効果も副作用も強い
抗がん剤を使うことが少なくありません。
次から次へと抗がん剤を切り替えているうちに、
いつしか効果の弱い抗がん剤しかなくなったり、
使える抗がん剤がなくなったりしてしまいます。
そしてそのころには、
患者さんは副作用に疲れ果て、
がんと闘う体力も気力も残っていない・・・
というケースが、実は多いのです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「病は気から」と昔からよく言いますが、
現代の医学からみた場合も
病気と精神が深く関係しているといえるそうです。
患者さんの気力の維持と、
抗がん剤の使用のバランスは
本当に苦悩する選択だと思います。
また治療の「やめどき」を決めることは
想像できないくらい、難しいことですよね。
治療法を決めたり、変更するときにできるだけ
1人で抱え込まないようにしてもらいたいと
思いました。
ー三浦とも子