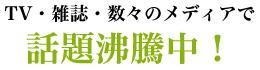FROM 帯津良一
1976年の当時食道がんの手術において、
食道と胃管との吻合部(ふんごうぶ)の
縫合不全(ほうごうふぜん)というリスクを
いつも背負っていなければならなかった。
では、縫合不全が生じたらどうなるのか。
唾液や食物が漏れ出して
周囲に膿瘍(のうよう)を形成する。
これがもし胸のなかで起こると
膿胸(のうきょう)になって致命的になる。
そこで頚部の浅いところで吻合して
近くにドレーンなるプラスチックの管を添えておく。
万が一漏れても、
汚いものがドレーンに沿って体外に排泄されるので、
膿瘍を形成するには至らす、
しばらく食べたり飲んだりを
ひかえているだけで治癒に向かってくれる。
ということで肺合併症より
やや遅れて発生する。
しかも食道がんの手術に特有の術後合併症が
この吻合部縫合不全なのである。
この合併症は
術後10日ほどして起こることもあるが、
ほとんどは7日以内に起こるので、
術後4、5日を経て肺合併症もなく
吻合不全の兆し(きざし)もないとなって、
患者さんは集中治療室から一般病棟に出ることになる。
新しく東京都のがんセンター的な役割を
担って出発した都立駒込病院には
それはすばらしい集中治療室を備えていた。
清潔な十分すぎる広いスペース。
ピーンと張りつめた空気のなかを、
足音を消して歩き回る看護師さんたち。
ところどころにスタンバイしている
欧米製の人工呼吸器。
スタイルはさまざまだがいずれも
ピカピカの新品であるところが頼もしい。
酸素テントの往時に比べて
なんとはたらきやすいことか。
術後の合併症で苦労することも
きわめて少なくなった。
広大な下町の人口をひかえて
手術件数も大学病院よりも多いくらいだ。
そのうえ食道がんの術後は
かならず集中治療室に入るので、
看護師さんとの意思の疎通も
十分すぎるくらいである。
自宅は埼玉県の川越市にあって
通勤に1時間以上かかるので、
夜間に不測の事態が起こると、
そう簡単には出てこられない。
そこで、自分の担当の患者さんがICUにいる間は
自宅に帰ることをせずにICUの当直室に
4日でも5日でも連泊することにしていたので、
意思の疎通もさらに高まるというものだ。
しかも不測の事態というものは
それほどしばしば起こるものではない。
そんな下手な手術はしていませんよというものだ。
夕食は外で1杯ということになる。
日勤を終えた看護師さんの
一人二人を誘って飲みに行く。
帰ってきて患者さんの様子を見て、
安心して眠りにつくということで、
またまた意思の疎通が高まるというものだ。
また、手術の流儀というものは
大学によって、また医局によって
微妙に異なるものだ。
だから他の医局の人といっしょに
手術をすることは多少抵抗があるものなのだが、
新生成った都立駒込病院では
そんな雰囲気は微塵(みじん) もなかった。
ここで、自分たちの手でがんを克服してみせるぞ
という気概が外科の医局に
充ちみちていたことが第一の理由。
もう一つの理由は、
酒好きが揃っていたことか。
連れだってよく飲み歩いたものだ。
お寿司屋さん、居酒屋さん、とんかつ屋さん、
天ぷら屋さん、中華屋さん、
そして小さな洋食屋さんと
潤滑油には事欠かなかった。
━━━━━━━━━━━━━━━━
◎編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━
今日は秋晴れ、風が気持ちがいいですね。
近くの小学校では、
運動会練習の真っ最中です。
運動が得意ではないのになぜか
運動会がとても好きだった私。
当日は張り切って
7時30分に登校していたことを思い出しました。
―三浦とも子