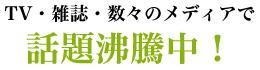FROM 帯津良一
それまで感染症の病院として
勇名をとどろかせていた都立駒込病院が
東京都のがんセンターとして
再出発をしたのが1975年。
当時、東京大学第三外科から
静岡県の共立蒲原(かんぱら)総合病院に
出向していた私に
都立駒込病院に赴任するように
医局長からの要請があり、
最初の1年間を非常勤医として勤務した後、
1976年5月に常勤医として赴任した。
その頃はまだ有楽町の駅の近くにあった
東京都庁で辞令を受け取った後、任地に直行。
バスを降りて、5月の青空に屹立する
新装成った病院を仰ぎ見たとき、
よし、ここでこの手で
がんを克服してみせるぞと
闘魂が胸に漲った(みなぎった)のを
いまでも鮮やかに憶えている。
外科の医師は総勢20数名。
今度の人事は学閥を排すために
全国津々浦浦から集められたという噂どおり、
出身大学は多彩をきわめていた。
私はというと東京女子医科大学
消化器センターからの2人と3人で
食道がんのチームを編制することになった。
食道がんの手術といえば
かつては難手術の一角を占めていた。
手術はすべて教授が執刀。
“新ちゃん”と呼ばれていた外科医1年生は
昼夜を忘れて術後の管理に走り回ったものである。
当時はまだ集中治療室(ICU)という制度はなかった。
大部屋の片隅に酸素テント
(患者さんの上半身をビニール・シートで覆い、
そのなかに加湿した高流量の酸素を送り込む装置)
をしつらえて、
術後の管理をおこなうのである。
術直後で意識が朦朧としているとはいえ、
閉所恐怖症の患者さんには
たまらないものだっただろう。
長い手術時間と多量の出血も相俟って
術後の合併症も決して少ないものではなかった。
肺炎や無気肺などの肺合併症には
いつも苦労していたうえ、
食道と胃管との吻合部(ふんごうぶ)の
縫合不全(ほうごうふぜん)というリスクを
いつも背負っていなければならなかった。
どういうことかというと、
右の胸を開いてがんを含めた
20センチほどの胸部食道を切除する。
ということは食道に欠損部が生じて
頚部の食道と胃袋が泣き別れの状態になる。
この欠損部を何かで補填(ほてん)して、
泣き別れを解消して初めて手術が完了する
というものである。
そのためにはどうするか。
お腹を開けて、胃袋をトリミングして
細長い胃管につくり変えたものを
胸部の後ろを通して頚部まで引き上げて
頚部食道断端(けいぶしょくどうだんたん)と
吻合するのである。
この胃管作製挙上という操作のなかで
大事なことは胃袋に対する
栄養血管を残して血流を温存することにある。
もし栄養血管を
損傷するようなことになれば、
胃袋は壊死(えし)におちいってしまって
使い物にならなくなるからである。
さらに血流を温存して
吻合できたとしても、
もともとお腹のなかにおさまっている
胃袋を頚部まで挙上するのだから
多少の血流不足は否めない。
吻合部の縫合不全リスクはどうしても高まる。
━━━━━━━━━━━━━━━━
◎編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━
近くの小学校でインフルエンザが
流行しているそうです。
この時期にインフルエンザ…
とびっくりしました。
冬は念入りにしていた
家族への手洗い指導も
ちょっと適当になっていたので(汗)
身がひきしまりました!
―三浦とも子