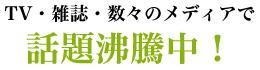【パーソナル健康学】No.131 (2014.7.18)
>>メルマガの購読はコチラから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
FROM おのころ心平
おはようございます。
おのころ心平です。
来週の日曜日、
7月27日、
おのころ心平、
北海道は札幌にて、
オープンセミナーを開催します!
ただいま早割&ペアチケット発売中。
お申し込みは、こちらへ!
※ ※ ※
さてさて、
血液型タイプ論シリーズで
お届けしています
「パーソナル健康学」。
前回の動物たちの血液型に続き、
今回は植物たちをみてみましょう。
【A型物質を持つ植物】
・アオキ(ミズキ科)
・ヒサカキ(ツバキ科)
・キブシ(キブシ科)
・ウバメガシ(ブナ科)
【B型物質を持つ植物】
・ツルマサキ(ニシキギ科)
・イヌツゲ(モチノキ科)
【AB型物質を持つ植物】
・スモモ
・ソバ
・コンブ
・ヒバマタ
・ガマズミ
・アセビ
・ウリカエデ
【0型の植物】
・ゴボウ
・ダイコン
・サトイモ
・ブドウ
・エノキタケ
・マンネンタケ
・スイカズラ
・ネズミモチ
・ナツハゼ
・ツバキ
・タカオカエデ
・マユミ(ニシキギ科)
・コブシ
・サルトリイバラ
・イチイ
※ ※ ※
いかがでしょう。
血液型物質は
人類にだけあるのではなく、
生物進化の歴史とともにありました。
血液型物質をはじめて
獲得したのは、細菌です。
およそ30億年前には存在したことが
化石で確認されている細菌たち。
ABO血液型物質は糖でできていますが、
糖の合成を可能にした原始生物のうち、
血液型物質の合成までできた生物が
細菌なのでした。
ご存知のように人間の腸には
100兆個もの細菌群が棲んでいますが、
そのひとつひとつに、
血液型物質があります。
たとえばB型の人間のお腹のなかで
A型血液型を持つ細菌群が増えると、
それは下痢の原因になったり、
ガスの原因になったりするかもしれません。
※ ※ ※
血液型物質は、
細菌
↓
植物
↓
動物
↓
人類
とバトンタッチされ、
進化と免疫系の高度化に
一役も二役もかってきたのです。
さあ、血液型シリーズも大詰めです。
7月22日(火)25日(金)の
あと2回でおしまい。
いよいよ病気と血液型の関係について
みて行きます。
PS
※8/24(日)、おのころ心平大講演会
「病気は才能」、まもなくです!
※定員400名、残席73名ですー