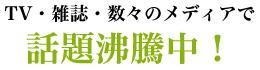【パーソナル健康学】No.245 (2015.1.25)
>>メルマガの購読はコチラから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
FROM 安永周平
先日、アドラー心理学を企業向けに
教えている小倉広さんの講演に
参加する機会があった。
別名「勇気づけの心理学」とも
言われるアドラーの教えは、
なるほど…と納得する事が多く、
改めて日々の行動で見直すべき事が
たくさんあるな…と勉強になった。
…っと(汗)。
人間、よくありがちだけど、この
「勉強になった」が実は曲者で
「いい話を聞いた」だけで終わると
せっかく学びを得ても、結局は
何も変わらず終わってしまう。
それだけは避けたい。
加えて、アドラー心理学は、
確かに素晴らしい教えだけど、
仕事においてはどうしても
理想通りにいかない事も多い。
「ほめるな、叱るな、教えるな」
それが、今回の講演のテーマで
確かに講演を聴くと納得できる。
とはいえ、緊急事態においても
それができるか…というと疑問だ。
一刻を争うような事態の時に、
スタッフにやるべき事を教えずに
自分で考えながらやってもらう
というわけにはいかないだろう。
だから、確かにいい話だったけど、
結局は理想論で、仕事の現場で
使うのは難しい…というように
結論づけてしまうこともできる。
でも、今回は「いい話聞いた」で
終わらないポイントを教わったので
あなたにもシェアしたいと思う。
* * *
それは、職場でアドラーの教えを
「実践しなくてもいい」ということ。
何を言ってんだ???
と思うかもしれないけれど、
結構、重要なポイントで。
実は、アドラー心理学の教えは
「企業・会社の中」で使われる
という前提では語られていない。
対人関係の問題を解決するために
とても優れた考え方ではあるけれど
それは、あくまで対人関係が
最優先であるという前提がある。
たとえば、会社においては短期的に
利益を出さなければ潰れてしまう…
という事態の時に、従業員間の
対人関係が最優先か?と考えると、
必ずしもそうでない場合もある。
会社が潰れそうな時に、社長が
適切な指示・命令ができなければ
本当に潰れてしまうだろう。
最終、従業員の雇用を守るために、
有無を言わさずに仕事をして
もらわなければならない事もある。
だから、経営者である社長は、
時と場合によっては当然、
指示する、教える、叱る…
ということだって必要になる。
つまり、アドラー心理学の枠に
収まりきらない決断も、時には
必要になってくるということ。
仕事においては必ずしも
絶対的なものではないのだ。
※ちなみに、アドラー心理学の教えは
子供を育てるケースで考えられている
* * *
大切なのは、その時の自分の行動が
アドラー心理学の枠の「外」の行動
であることを自覚しておくことだ。
今の自分の行動は、対人関係を
悪くしてしまっているが、これは
仕事において必要なことだから…
「ここから先は、仕方ないけど
アドラー心理学はは無視しよう」
と、自覚のうえで行動する
ということが大事なのだと。
無自覚のままで、対人関係を
損なっていることが問題であり、
自分で考えた上での判断ならば、
その判断は尊重されるものだ。
偉大なアドラー心理学ですら、
僕らの人生における「万能薬」
にはなり得ないのだ。
だからこそ、今の自分自身に
本当に必要かどうかを考えて
自覚的に活用しなければならない。
* * *
自分の感情や行動に無自覚か、
自覚的か…という違いは大きい。
僕ら人間は、生きていれば、
時々怒ったり、イライラしたり
することだってあるだろう。
それ自体は悪い事じゃない。
ごくごく、自然な反応だと思う。
でも、イライラしてい時、
ストレスを感じている時こそ
自分を客観的にみながら…
「あぁ、今自分怒ってるな」
と自覚できる、気がつけるほうが、
自分にとってよりよい行動を
選択できることにつながると思う。
そうすることで、もしかしたら
別の視点が持てるかもしれない。
さっきまで怒っていたけれど、
実はそんなに大した問題では
ないのかもしれない。
笑い飛ばしたほうが
いいのかもしれない。
そう思えれば、日々の生活で
ストレスってずっと減ると思う。
そのほうが、日々の生活は
楽しくなると思うのだが…
いかがだろうか?
なんか、そんなことを
考えさせられた講演だった。
PS
ストレスを減らしながら、
残ったストレスが軽くなれば、
毎日はとてもハッピーだと思う。
ストレスを軽くするには、
こちらがとってもオススメ
※なんせコレ、とても気持ちいい♪