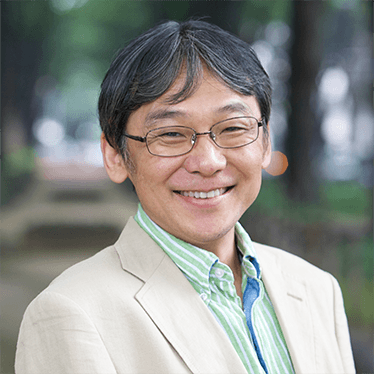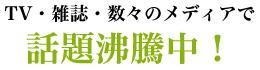FROM 川嶋朗
これまで認知症のことをお話ししてきましたが、
この認知症を引き起こす原因となる
病気の1つがアルツハイマー病です。
アルツハイマー病から
認知症を引き起こした場合は、
アルツハイマー型認知症となります。
患者数は2011年で36万6000人。
(厚生労働省資料より)
糖尿病などの生活習慣病の増加に伴い、
患者数は日を追うごとにふえているのが現状です。
認知症のなかで最も多い症例が
アルツハイマー型認知症で全体の66%、
次に脳血管性認知症が20%、
レビー小体型認知症が6%という報告があります。
このアルツハイマー型認知症は、
さらに2種類に分かれます。
遺伝による罹患が確認されている
家族性アルツハイマー病
(若年性アルツハイマー病のほとんど)と、
65歳以上の人が発症する
アルツハイマー型老年認知症です。
ここでは、
「アルツハイマー病」「アルツハイマー型認知症」
という呼び名がでてきますが、
以前は発症年齢で分類されていました。
しかしながら、症状はほぼ同じで、
病理学的にも同じものであることから、
近年ではほとんどの場合これを区別しません。
アルツハイマー病は、
1906年にドイツの精神医学者
アロイス・アルツハイマーによって
はじめて報告された病気ですが、
発生原因やメカニズムについては
未だ研究途上で、
いくつかの仮説に基づき、
治療方針が立てられています。
脳のなかの記憶に関係する部分
(海馬、頭頂葉、側頭葉)に
βアミロイドというタンパク質の一種が
毒性を持って蓄積し(これを老人斑とも呼ぶ)、
またタウというタンパク質が
神経原線維変化を引き起こして
脳を萎縮させ、神経細胞を
死に至らしめるという
「アミロイド・カスケード仮説」
が主流となっています。
ほかにも、「オリゴマー仮説」などがあります。
日本では、この
アミロイド・カスケード仮説に基づいた
ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン
などといった薬が認可されていますが、
どれも神経細胞が変性していくことを
抑える働きがあるわけではありません。
進行を若干遅くする、
神経伝達物質の分解をおさえ込む、
という補助の役割しかないので、
医師は効くと思って
処方してはいないのが現状です。
高価でもあるので、
初期を過ぎた患者さんには
投薬を止めることもあります。
フランスでは、昨年6月1日、
フランス厚生省(社会問題・健康省)が、
「現在、アルツハイマー病の治療のために使われている薬、
ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン、メマンチンを、
8月1日より医療保険のカバーから外す」
と発表しました。
世界的にふえている
アルツハイマー病に対して、
たとえばドイツでは、
イチョウの葉のエキスが
治療薬として認可されています。
血流をよくする効果がありますが、
やはりこれも神経の変性に
直接効くものではなさそうです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公園でセミの抜け殻を集めている
子供を見かけました。
虫が苦手な私でも
セミの抜け殻を見つけると
なんだか嬉しくなってしまうものです。
そっと扱わないと崩れてしまうところが
「宝物感」のポイントかもしれません。
ー三浦とも子