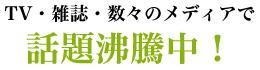FROM 帯津良一
気功という言葉はすでに知っていた。
わが国における気功の草分け的な存在としての
津村喬さんと星野稔さんのお名前も記憶していた。
しかし、実際の気功を目にしたことはなかった。
「…その気功を見学することは可能ですか?…」
「ああ、いいですよ」
と時計を見て、
「いま、ちょうど中庭でやっていますよ。
…案内させましょう」
中庭では10人ほどが円陣を組んで
練功(れんこう)に余念がない。
一見して、これは呼吸法だ!と思った。
そして、しばらくして、
気功こそががん治療における
中国医学のエースだと直観したのである。
少しでも体験して、できれば
簡単な功法を身につけて帰国したいと考えて、
張益英先生と謝玉泉先生に相談してみたが、
一向に埒(らち)が明かない。
西洋医学畑の人にとって気功は
まだ縁なき衆生(しゅじょう)なのだ。
しかたがないので、
少しでも文献を漁って帰ることにした。
まずは北京飯店からほど近い王府井(わんふうちん)にある
新華(しんか)書店に入ってみた。
折しも文化大革命が終わってまもなくのことである。
店内は知識欲に目覚めた人々によってごった返していた。
気功に関する書籍はおよそ20種類。
これを余すところなく買い込んだものである。
中国医学といえば漢方薬と鍼灸という治療医学と
気功と食養生と言う養生医学の
4本柱からなる。
北京市立がんセンターの徐光偉院長は
外科医であるうえに、
以前、都立駒込病院を訪れたこともあって
私とは面識のある仲である。
私のこのたびの訪中の意図も
十分に理解していただいていたようで、
まず、センターで漢方薬部門のヘッドを務めていた
李岩(りがん)先生を紹介してくれた。
年の頃は私とほぼ同じか。
どちらかといえば小柄な好人物である。
まずは彼の担当している病室、
すなわち主として漢方薬でがんの治療を
おこなっている患者さんたちの病室に案内された。
そのなかに日本語の話せる中年男性で
胃がんの患者さんがいた。
いくつかの質問をさせてもらったが、
漢方薬治療を心地よく受け入れている風情が印象的であった。
参考のためにと彼が服用している処方を
メモ用紙に書いて手渡してくれた。
いまでも忘れられないその処方は
“竜葵(りゅうき)、蛇莓(じゃばい)、玉金(ぎょくきん)、
当帰(とうき)、丹参(たんじん)、白花蛇舌草(びゃくかじゃぜつそう)”
というもので、李岩先生はこれを
白蛇六味丸(びゃくじゃくろくみがん)と呼んでいた。
いまでもわが病院の主要処方である。
1日、バスを仕立て、
万里の長城にハイキングと洒落込んだが、
その際も李岩先生は同行して
往復の時間を利用して漢方薬談義に花が咲いたものである。
彼は決して威勢のいいことは言わない。
淡淡と喋っていく。
この日1日で彼とは旧知の間柄のように打ち解けてしまう。
後に私の病院に何回となく足を運んでくれて、
わが病院の漢方薬部門の基礎を築いてくれたことは
感謝に堪えない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
たまにとっても食べたくなるのが
卵かけご飯です。
ご飯に卵をどうかけるか…に
性格があらわれるという
奥深い食べ物。
今日10月30日は
「たまごかけごはん」の日です!
ー 三浦ともこ